京都府リカレント教育推進機構
- 京都府リカレント教育推進機構 令和7年度 R&D問題懇話会
-
有料

グローバル競争が激化する今日、新たな事業革新の中心として、R&D部門の重要性がますます高まっております。
このような中、本会・R&D問題懇話会では、研究開発に関する課題の共有化や先進企業の事例研究を通し、業務の効率化を目指し、活発な活動を展開いたしております。
貴社におかれましても、今後のR&Dマネジメントに活用いただければ幸いに存じます。
奮ってご参加くださいますよう、ご案内申しあげます。
- 京都府リカレント教育推進機構 第11回ELSIカフェ「ゲノム情報による「不当な差別」とは何かについて考える」
-
無料
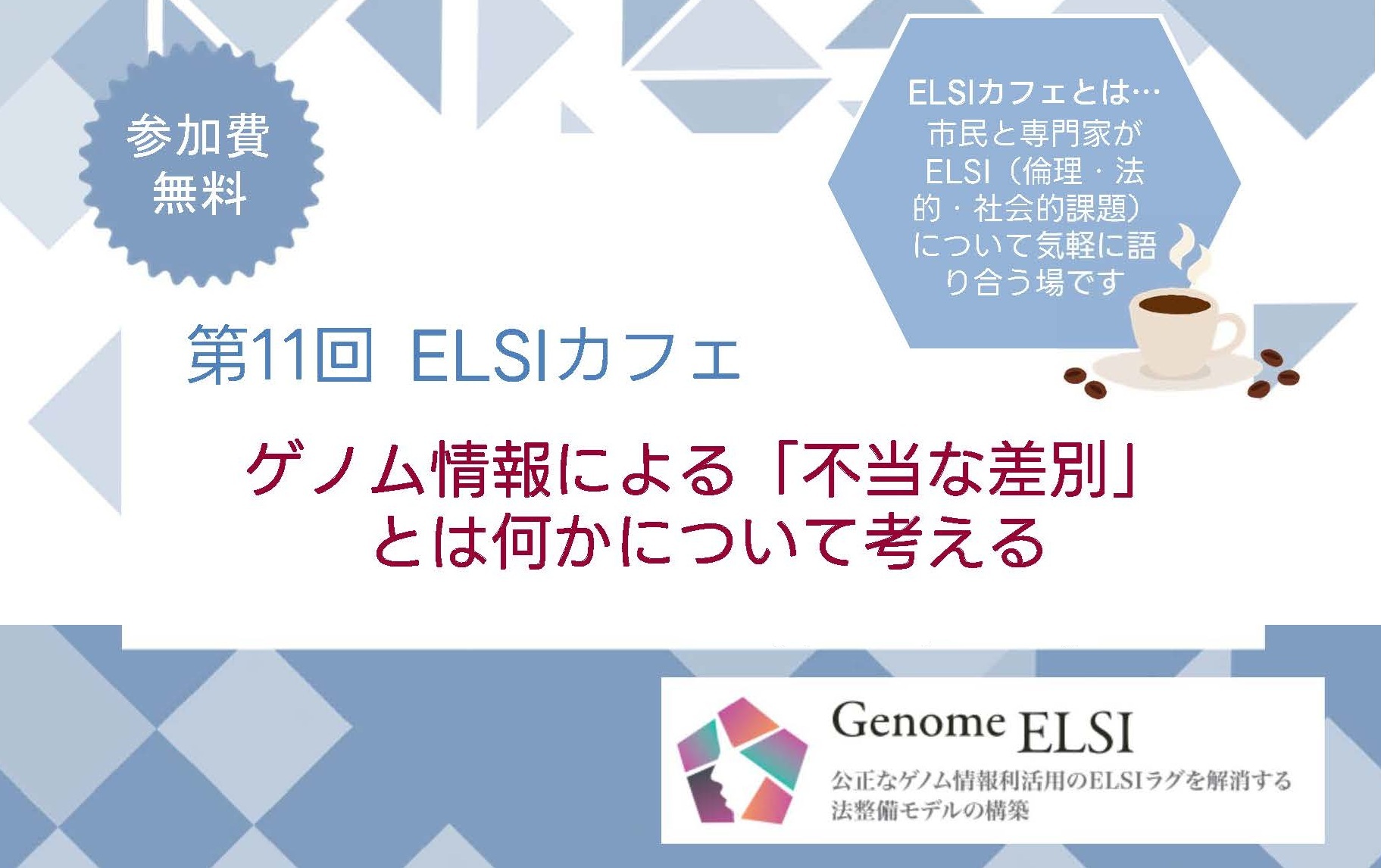
本研究プロジェクトでは、保険や雇用等の非医療分野において遺伝子差別を受けないための日本におけるモデル法案を作成中です。
今回のELSIカフェでは、ゲノム情報による「不当な差別」とは何かについて参加者全員で議論し、非医療分野における遺伝子差別禁止のモデル法案の作成を進めます。
- 京都府リカレント教育推進機構 機械加工技術コース
-
有料

昨今、インダストリー4.0、IoT、AI、自動運転技術、ロボット化等、最先端技術の技術革新が急速に進む中、機械加工の分野におきましても、その製造スタイルが大きく変化しつつあります。
そこで、この度、本会ではこれらの環境変化への対応や最新動向の習得のために、「機械加工技術コース」を開講いたします。
- 京都府リカレント教育推進機構 中小企業技術幹部交流会
-
有料

産業界における企業間競争が激化する今日、新たな事業の柱を生み出す事業革新の必要性が増しております。このような中、本会・中小企業技術幹部交流会では、技術・開発関連部門長及び同等の管理職を中心に、技術・開発に関する諸問題について、企業や施設訪問、意見交換等、活発な活動を展開しております。
つきましては、貴社におかれましても、事業革新へのご参考にしていただければ幸いに存じます。
奮ってご参加下さいますよ
- 京都府リカレント教育推進機構 電子システム研究科・メカトロニクス研究科 研修生募集
-
有料

特になし
- 京都府リカレント教育推進機構 第10回ELSIカフェ「ゲノム医療推進法に基づく基本計画について考える」
-
無料
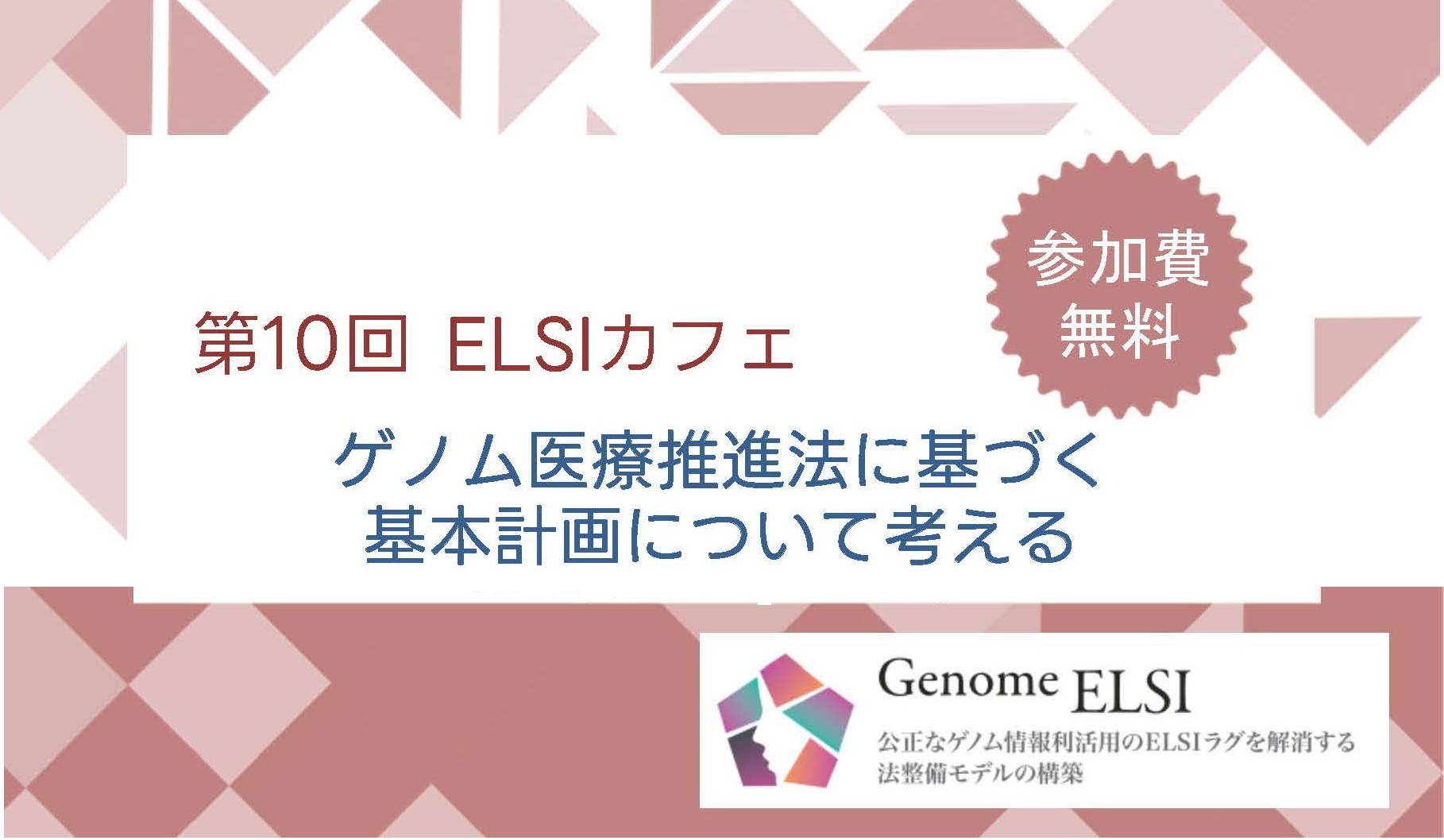
2023年にゲノム医療推進法が施行され、厚生労働省のゲノム医療推進法に基づく基本計画の検討に係るワーキンググループによりゲノム医療施策に関する基本的計画案が提示され検討されています。
今回のELSIカフェでは、基本計画案の生命倫理への配慮およびゲノム情報による不当な差別等への対応の確保について一緒に考えてみませんか。
- 京都府リカレント教育推進機構 医師事務作業補助者基礎研修
-
有料

15歳以上の方ならどなたでも。(中学生を除く)
- 京都府リカレント教育推進機構 知って役立つ!最新・労働法入門~雇う・雇われる人の日常に関わる大事なルール~
-
有料
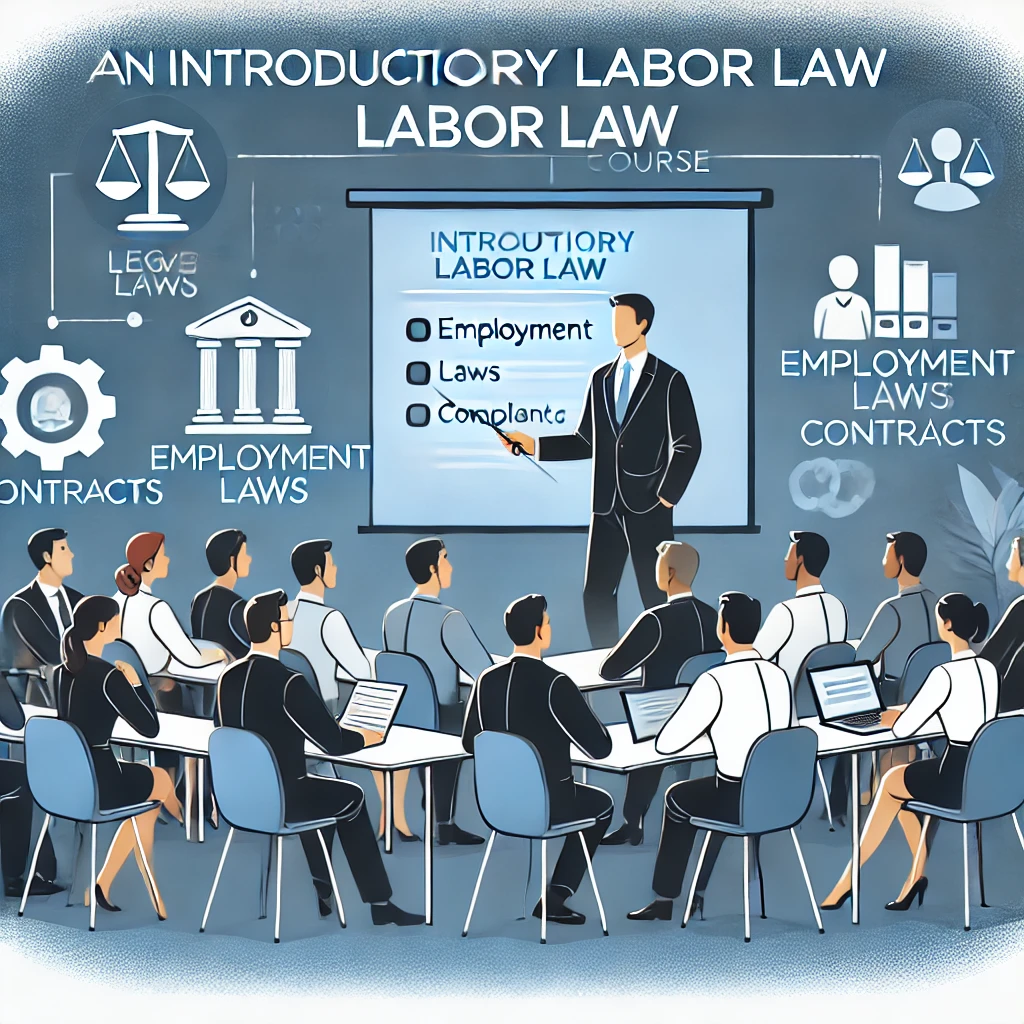
労働法は、頻繁に実施される法改正や新しい判例について常に注目する必要があります。昨今の労働基準法、労働安全衛生法、労災保険法、労働契約法、育児・介護休業法、パートタイム・有期雇用労働法などの改正点や、働き方の多様化を受けて制定されたフリーランス新法の内容を確認するとともに、重要判例も折り込みながら、基本的枠組みとその考え方について、初心者にも分かりやすく解説します。
- 京都府リカレント教育推進機構 音で楽しむフランス語入門~日本昔ばなしを使って~
-
有料

日本の昔ばなしを日本語とフランス語で音読しながら、楽しく気軽にフランス語に親しみ、フランス語の発音を身に付けます。
クラスはゆっくり進み、日仏対訳のテキストには日本語の解説も付いているため、初めての方でも受講可能です。アルファベットの発音の仕方や読み方、文法を知らなくても、日本語でストーリーを理解しながら先生の声をまねて音読することにより、少しずつ理解が深まります!講師は日仏バイリンガル!- 講座種別
- 新しい活躍の場を目指す
- 会場
- ラボ-ル学園(公益社団法人京都勤労者学園)京都市中京区四条御前ラボール京都3F
- 課程区分
- 教養
- 開催日時
- 2025年04月21日 18:30~20:30
- 京都府リカレント教育推進機構 情報学リスキリング講座
-
無料
.png)
AIの発展とそれらを駆使したDXが注目される現代社会において、ワープロ、メール、プレゼンテーション等のソフトウエアが使えるだけでは先端的な情報技術の活用やDXの推進を十分に検討することはできません。
本講座は、本学工学部情報工学科における授業のエッセンスを集結しており、これからの情報化社会をリードするために必要な情報学の体系的知識の習得を目指せます。ふるってお申し込みください。